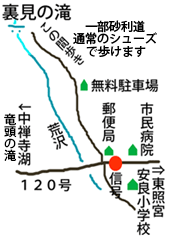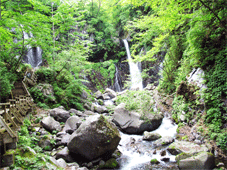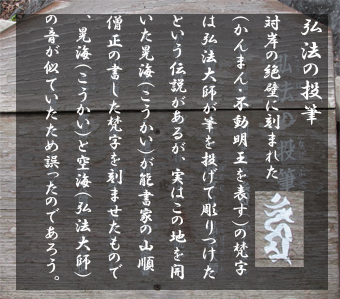この日、今年何度目かの日光、芭蕉の跡を辿ります。日光山から122号国道を中禅寺湖方面に進み、日光市立病院の信号で右に曲がると裏見の滝の駐車場があります。駐車場から20分ほどで滝が見えてきます。私は途中で道を間違え沢沿いの道を進んで右岸(進行方向の左岸)へと渡ってしまいました(道は左岸・沢の右でした)。水源地への道であったようですが、戻るのも面倒なのでそのまま右岸を進んで、最後はガレ場を下って滝下へと辿りつきました。細々とつづく獣道にかなり大汗をかいてしまいました。
下から見る裏見の滝は安っぽい絵葉書の絵のようでなにか面白くありません。芭蕉が書いたように滝の裏への道を登って、滝の懐に入って芭蕉の姿をしのびました。水の落ちる音が岩屋に覆いかぶさってくる様はまさに『滝に籠るや・・』の興趣でした。滝の裏の岩屋まで登らなければこの句は生まれなかったでないかと強く感じました。奥の細道の文から見えてくる芭蕉なら、きっと水に濡れながら滝の裏まで登ったと私は思いました。
2010,06.07
日光の芭蕉・元禄二年(1689年) |
||
旧暦 |
新暦 |
場所 |
| 4月1日 | 5月19日 | 鹿沼を出て日光上鉢石宿の五左衛門方に滞在する。日光山参拝。本文中は30日と書かれています。 |
4月2日 |
5月20日 | 裏見の滝から感満ケ淵を散策。一旦宿に戻り、瀬尾・川室を経て、大渡りで鬼怒川を渡る。日光北街道を進み玉入で泊る。 |
| 4月3日 | 5月21日 | 玉入より坂道を登り下りして山を越える。矢板に出て沢集落の辺りで那珂川の支流・箒川を越えて黒羽に向かう。 |
『奥の細道・裏見の滝』文章
裏見の滝
二十余丁、山を登ツて滝有。岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭(へきたん)に落ちたり。岩窟に身をひそめ入て、滝の裏よりミれバ、うらみの滝と、申伝へ侍る也。
暫時(しばらく)は滝にこもるや夏の初
曽良旅日記の裏見の滝と憾満ケ淵(かんまん)ケ淵の記述
一 同二日 天気快晴。辰ノ中剋、宿ヲ出。ウラ見ノ滝(一里程西北)・ガンマンガ淵見巡。漸ク及午。*憾満ケ淵(かんまん・含満ケ淵とも表記):曽良はガンマンガ淵と書いていますが地元では晃海(こうかい)大僧正創建の伝承等から カンマン・憾満が正しいとされていますのでそれに倣います。
村の4月・5月・6月の花・スライド・ショーは下記の画像をクリックしてニコンのページからご覧ください。 画面下部の |
 絵葉書のような構図の裏見の滝です。写真真ん中の草の間の黒い空間が凹んで岩屋になっています。滝の裏へは草付の辺りから登って行きます。
絵葉書のような構図の裏見の滝です。写真真ん中の草の間の黒い空間が凹んで岩屋になっています。滝の裏へは草付の辺りから登って行きます。
 |
 |
| 草付を右に登っていくと鉄の階段があります。その先に不動明王だと思いますが、石像が鎮座した畳2畳ほどもある快適な広い自然の岩屋が広がっています。芭蕉が此処まで登って来たからこそ『滝に籠るや・・・』のイメージが湧いて来たに違いないと思いました。下からただ見上げていては『籠もる』場所が見つけられません。昔、岩が崩落しない時はもっと先まで行けたとの事です。 |
 |
 |
| 鉄の階段を登っていくと綺麗な岩室が現れます。あたりは流れ落ちる滝の轟音、不動明王がそれを静めてくれているようです。この岩室が芭蕉がたった場所ではないでしょうか。作品であるからには話を誰かに聞いてイメージを膨らませた事も多いに有るかとも思えますが。 |
芭蕉が『岩窟に身をひそめ入て、滝の裏よりミれバ・・・』と書いた岩窟は不動明王の石像が祀られたこの場所に違いないと思えてきます。此処から見える奔流する水の様はまさに『岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭(へきたん)に落ちたり。』の通りです。私は、誰も居ないこの異空間の中で芭蕉との心の交流を感じてしまいました。

|
||||||||
|
||||||||
 |
|
|||||||
芭蕉は歌枕の地を尋ねて古の歌人と歌に思いを馳せようとしたそうですが、多くの地はその面影さえ留めていませんでした。時の流れの無常を思いさらされたに違いありません。芭蕉から300年後、奥の細道の地を辿る私たちが同じ思いを抱いているとは・・・当然の巡り合わせです。ただ時折芭蕉の影が強く浮かぶ地に立つ僥倖に遭遇しますが、この裏見の滝の岩屋がまさにそれでした。
もしかしたら芭蕉の訪れた当時と大きく変わっているのかもしれませんが、岩屋に轟きわたる滝の音は芭蕉との一体感で私の全身を包み込んでくれるのです。もしかしたら誤解かもしれません、そうであってもこの自然が強い力で芭蕉の心を感じさせてくれるのです。その場に立った幸せを感じた旅でした。帰路安良沢小学校の句碑を見せていただきました。駐車場を通る二人連れの方に良いでしょうと云うので ゆっくりと見せていただきました。その後、憾満ケ淵(かんまん)ケ淵に向かいます。
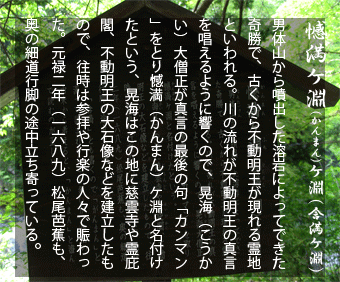
奥の細道本文には憾満ケ淵(かんまん)ケ淵についての記述はありません。僅かに曽良の旅日記に「ウラ見ノ滝(一里程西北)・ガンマンガ淵見巡。漸ク及午。」とあるのみです。大日堂跡についてはその記述が見られませんが、綺麗な吊橋を渡って散策する事をお勧めします。
車で憾満ケ淵の無料駐車場まで行くのはかなり分かりにくい場所です。神橋から中禅寺湖方面に向かうと、すぐ大谷川と120号線がY時に分かれる場所があります。そこを左に入ります。千姫物語という旅館が一つの目印になります。裏手の旅館の砂利の駐車場を突っ切るように道が付いています。大谷川を小橋で渡り道なりに進むと公園の無料駐車場に突き当たります。ここに車を止めて公園の中を歩いて散策することになります。![]() 2010,06.07
2010,06.07
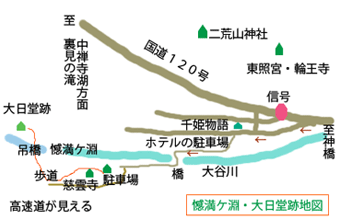 |
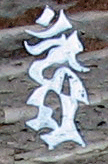 この梵字が名憾満ケ淵(かんまん)ケ淵の由来の梵字です。弘法(空海)の投げ筆の伝承もこの梵字が由来です。1654年晃海大僧正が人の及ばない力を示す大谷川の激流の霊的雰囲気の右岸一帯に、慈雲寺を建立した場所です。 この梵字が名憾満ケ淵(かんまん)ケ淵の由来の梵字です。弘法(空海)の投げ筆の伝承もこの梵字が由来です。1654年晃海大僧正が人の及ばない力を示す大谷川の激流の霊的雰囲気の右岸一帯に、慈雲寺を建立した場所です。 |
慈雲寺 |
|
 |
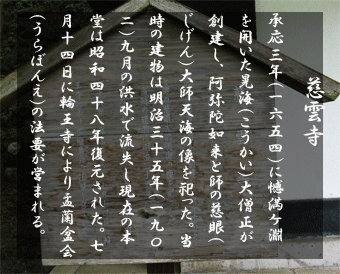 |
 上の写真は無料駐車場です。公園の道が慈雲寺への山門に通じています。憾満ケ淵(かんまん)ケ淵の右岸は慈雲寺の境内と云う事になると思います。しばらく進むと大きな川の流れの音が轟いてきます。 上の写真は無料駐車場です。公園の道が慈雲寺への山門に通じています。憾満ケ淵(かんまん)ケ淵の右岸は慈雲寺の境内と云う事になると思います。しばらく進むと大きな川の流れの音が轟いてきます。 |
 |
 慈雲寺の前を過ぎると大きな水の音が右手から聞こえてきます。憾満(かんまん)ケ淵は男体山から流れ出た溶岩が複雑な様相を作る渓谷です。およそ100メートル程度が見所です。大日堂跡へ向かう道から見る事が出来ます。
慈雲寺の前を過ぎると大きな水の音が右手から聞こえてきます。憾満(かんまん)ケ淵は男体山から流れ出た溶岩が複雑な様相を作る渓谷です。およそ100メートル程度が見所です。大日堂跡へ向かう道から見る事が出来ます。その他の慈雲寺内の見所 |
|
 |
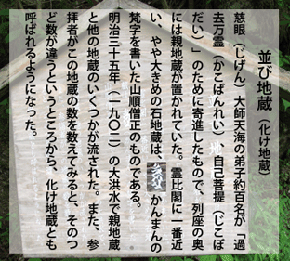 |
|
|
  |
|
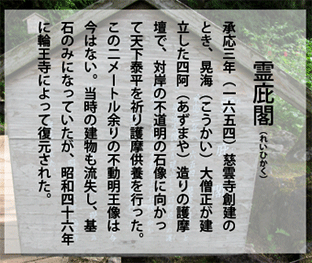 |
|
 |
 |
| 憾満(かんまん)ケ淵を右に見ながら進むと右に大日堂跡の標識。綺麗な吊橋を渡ると大谷川が一望できます。 |
 大日橋から憾満(かんまん)ケ淵の激流の見えます。振り返れば日光の山々が見えるのでしょうが今日は遠望が利きません。こんな有名な場所でもない大谷川にもかなりの外人が見物に訪れていました。 大日橋から憾満(かんまん)ケ淵の激流の見えます。振り返れば日光の山々が見えるのでしょうが今日は遠望が利きません。こんな有名な場所でもない大谷川にもかなりの外人が見物に訪れていました。 |
|
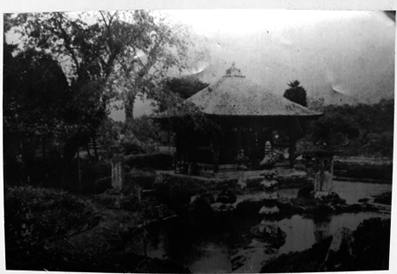 |
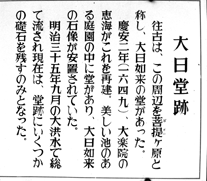 |
| 芭蕉の旅は1689年の事ですので1649年に再建された大日堂は存在した可能性があり、そうならば訪れた可能性もあるかもしれません。唯曽良の旅日記にはその記載が見られません。 | |
 |
 |
| 明治時代の大水害で流れた大日堂の基礎の石が数個残されていました。あたりの景色は再現されたようです。ここに芭蕉の句碑があります。 |
 |
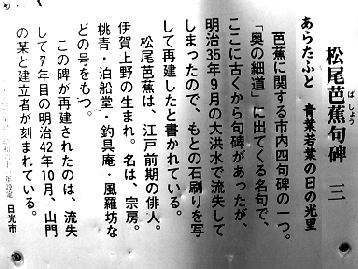 |
|
|
裏見の滝・憾満(かんまん)ケ淵と芭蕉の足跡をたどる旅は、水音が道連れです。それも常ならざる轟音、元禄時代にはもっと幽玄な場所であった日光の景色に立つ二人はしばし言葉を忘れたのではないかと思いました。私も一旦上鉢石宿にもどり、芭蕉の足跡を探す旅を続けたいと思います。*日光の細道④玉入宿に向かって瀬尾・川室から大渡りで鬼怒川を渡ります。近日中に掲載申し上げます。