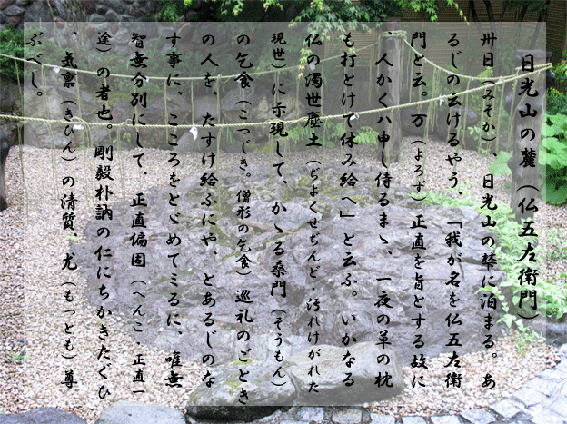
日光山の麓(仏五左衛門)
卅日(みそか)、日光山の梺に泊まる。あるじの云けるやう、「我が名を仏五左衛門と云。万(よろず)正直を旨とする故に、人かくハ申し侍るまゝ、一夜の草の枕も打とけて休み給へ」と云ふ。いかなる仏の濁世塵土(ぢよくせぢんど・汚れけがれた現世)に示現して、かゝる桑門(そうもん)の乞食(こつじき。僧形の乞食)巡礼のごときの人を、たすけ給ふにや、とあるじのなす事に、こころをとゞめてミるに、唯無智無分別にして、正直偏固(へんこ・正直一途)の者也。剛毅朴訥の仁にちかきたぐひ、気禀(きひん)の清質、尤も尊ぶべし。
一 四月朔日 前夜ヨリ小雨降。辰上刻、宿ヲ出。止テハ折々小雨ス。終日雲、日光ヘ着。雨止。清水寺ノ書、養源院ヘ届。大楽院ヘ使僧ヲ被添。折節大楽院客有之、未ノ下剋迄待テ御宮拝見。終テ其夜日光鉢石町五左衛門ト云者ノ方ニ宿。壱五弐四。
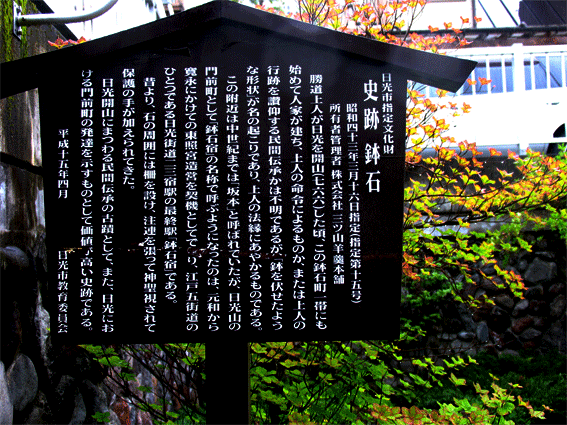

物語では30日と書きますが、実際は4月1日、鹿沼から日光・上鉢石(はついし)宿に着き、同日『五左衛門』に宿泊します。宿に寄らずにそのままの姿か、又は荷物を置いて旅の埃を落として日光山に詣でたと思われます。私の推測は、幕府にとって特別の霊域である日光山、芭蕉はまず宿を決め、そこに荷物を預けて旅の埃を払い気持ちを切り替えて参拝したのではないかと思っているのです。
翌日、裏見の滝を見学する折荷物を宿に置いて帰路立ち寄った事、五左衛門の親切な人柄もこの推論を後押ししているのです。ここに物語創作上の創意工夫があるとも言われていますが、素直に読めば五左衛門・日光山この順序になるのです。芭蕉程の文章を書く人なら一言二言、言葉を交わすだけでおおよその人間の心が分からないわけはないと思うのです。午の刻(11時から1時の間・昼飯時です)に鉢石に着いたと云う曽良の旅日記に僅かな手掛かりが残るばかりです。勿論素人の想像ですので大きな間違いかもしれない事をお断りもうしておきます。
写真は現在も日光市内に残る鉢石宿の名前に由来する大きな自然石の遺構です。
2010,05.31
日光の芭蕉・元禄二年(1689年) |
||
旧暦 |
新暦 |
場所 |
| 4月1日 | 5月19日 | 鹿沼を出て日光上鉢石宿の五左衛門方に滞在する。日光山参拝。本文中は30日と書かれています。 |
| 5月20日 | 裏見の滝から感満ケ淵を散策。一旦宿に戻り、瀬尾・川室を経て、下写真の大渡りで鬼怒川を渡る。日光北街道を進み玉入で泊る。 |
|
| 4月3日 | 5月21日 | 玉入より坂道を登り下りして山を越える。矢板に出て沢集落の辺りで那珂川の支流・箒川を越えて黒羽に向かう。 |
奥の細道は事実の羅列ではなく、物語として書かれているのですから事実を知ること以上に、面白いかどうかが大切な事だと思っています。素直に物語を読み楽しむ事が第一、その裏の事実は添え物だと(あまりそれにひっぱらられる事は避けたいと思っています)云う気持ちで素直に本文を読もうと思います。芭蕉は3月の終わりに日光・鉢石宿に着いたと書いています。物語は若葉のそよぐ4月、霊場へと舞台がぐるりと回るのです。 日光の段では、水が物語の大きな縦糸に感じます。裏見の滝・感満が淵は大谷川に注ぎやがて鬼怒川となり利根川となります、そして箒川は那珂川となります。物語の中で水音が絶える事が無いように感じました。 |
||

芭蕉の上鉢石町からの道筋について:芭蕉と曽良は日光に2泊した後黒羽を目指します。私は、二人は上鉢石町から大横町・虚空蔵尊の生活道路から大谷川を見ながら20丁程下り(地図中茶色の線)左岸へと渡ったのではないかと想像をたくましくしています。大横町に掲げられた1662年の八王子千人同心の話は私の想像を更に刺激してくれます。それは芭蕉が訪れる27年前の話です。そして毎年4月15~17日に行われる京都からの例幣使の到着には間がありますが、その準備の為の幕府・朝廷の公的な往来・治安維持などは始まっていたのではないかと云う事もこの想像の楽しみを後押ししてくれています。そしてなにより、芭蕉の話を知る以前から私は矢板から日光北街道を通り日光を例年のごとく何度となく行き来しておりましたが、偶然にもこの道を利用していたのです。勿論、個人的な、それも現在の経験を演繹するなど慎むべき事は重々承知していても、つい成程と思ってしまうのです。
芭蕉は鉢石宿(はついし・現日光市街地・鉢石町)に宿を取ります。この遺跡の近くのどこかだと思われますが、諸説があって特定は難しいようです。主の仏五左衛門の人柄についての考察に見られる、奥の細道の旅での地元の人々との活き活きとした交流が物語に真実味をもたらしているように感じるのです。そこでは何気ない風景・歌枕そして人間の生活が程よく組み合わされ、芭蕉の跡をたどる私にはその地での思いが更に深まります。
上の「鉢石」説明版にあるように、日光山の門前町・鉢石(はついし)宿に勝道(しょうどう)上人開山の伝承として大切に残されている幅3メートルほどの石が、ここに宿場のあったことを伝えています。今は世界遺産に登録された世界的な観光地として海外からも人々が訪れる町となっています。この鉢石の遺跡は神橋から市街の日光街道を今市方面(市役所方面)に300メートル程下ると市役所反対側の日本生命ビルの角を左に下ったところにあります。
2010,05.31
世界的な観光地・日光街道に面したメイン・ストリートは当時の面影など微塵も感じられないようです。私がこの辺りを訪れる時は、混雑する表通りを避けて裏通りを使って東照宮の初詣などに出かけます。この裏通りには杉の巨木が境内に見える神社、大横町の歴史を書いた看板などが見られて僅かながら往時の面影を感じられるのではと前から気になっていました。
奥の細道の跡を訪ねる楽しさを知ってから尚更この裏通りに興味を持ってきました。今日は駐車場に車を入れてゆっくりと路地から通りまでを歩いてみました。大きな間違いを犯しているのを危惧しながらも、芭蕉の通った道を想像する事は最も楽しみな事です。この大横町を歩きながら芭蕉の後ろ姿を目にうかべて見ました。
『芭蕉の日光から鬼怒川・大渡りまでの道との関連について』
曽良の旅日記を読んで、五左衛門は近道を教えたのだとの思いがすぐに浮かびました。そして近道なら一尺でも距離の短い道を教えたのではないかと思うので、表通りが混雑していれば(4月15日、毎年行われる京都からの例幣使の到着には間がありますが)尚更このような生活道路を教えたと考えてもおかしくはないと思ったのです。日光街道から芭蕉の句碑がある高野家(仏の五左衛門の可能性の一つとも言われるのですが)の路地を抜けると20~30メートルほどでぽっとこの裏通りに出ます。この道は大谷川に沿って今でも霧降橋の交差点まで続いています。
一般的に川は生活の大切な場所ですから、色々な道、微かなふみ跡のような、が続いていて、大谷川の向こうに渡る踏み石や浅瀬・丸太の仮橋が無いと考える方が難しいと思うのです。東照宮への参拝等から上鉢石宿に泊ったと思われる宿から、曽良旅日記の約二〇丁を参考にすると現在の『宝殿』の辺りで大谷川を左岸に渡り、出来る限り近道で瀬尾に向かったと思えてなりません。宝殿には現在も歩行用の小さな橋が大谷川に掛っているようです(霧降橋の上流部でそのような橋をみましたが宝殿のものは地図で見つけただけですので確認はしていません)。
私にはそのような想像を楽しむだけの観光地ズレしていない街並みながこの辺りに広がっています。芭蕉の訪れた1689年には上鉢石宿の一本裏通りには、八王子同心が務める「火の番屋敷」等の公的な屋敷を中心に町が完成していたと思われます。
 表通りから入った大谷川右岸に沿った裏通り、大横町の説明板のある角に小さな社があります。此処で道は大きな角を作っています。眼下に大谷川が指呼の間に見えます。
表通りから入った大谷川右岸に沿った裏通り、大横町の説明板のある角に小さな社があります。此処で道は大きな角を作っています。眼下に大谷川が指呼の間に見えます。
この裏道を芭蕉が向かった瀬尾方面・東に向かうと1640年建立の虚空蔵尊の由緒ありそうな社が右に現れてきます。
 大横町の由来を書いた看板です。前から気にはなっていましたが、車を止めるスペースがありません。今回は少し離れた広い場所に車をとめてじっくりと読んでみました。
大横町の由来を書いた看板です。前から気にはなっていましたが、車を止めるスペースがありません。今回は少し離れた広い場所に車をとめてじっくりと読んでみました。
昔は今の道ほど広くはなかったそうですが道があったとの事です。芭蕉は表の日光街道ではなく、この大横町の大谷川沿いの道を通った可能性が高いと想像を楽しんでいるのです。
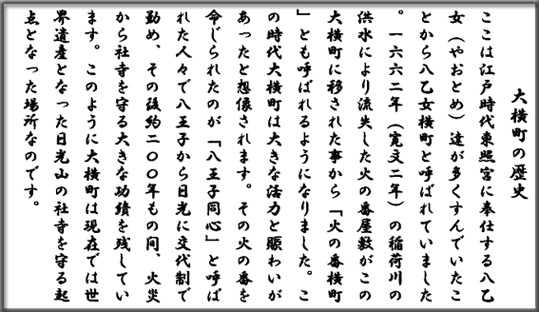
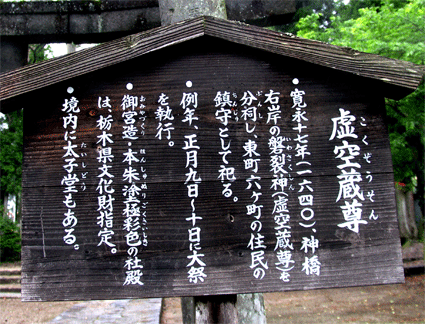
 芭蕉が1689年に訪れた時、日光街道と大谷川右岸の間には、このような街並みが日光街道に並行して広がっていたのです。この社には大きな杉の木と、小さいながら美しい社殿を持った神域がありました。
芭蕉が1689年に訪れた時、日光街道と大谷川右岸の間には、このような街並みが日光街道に並行して広がっていたのです。この社には大きな杉の木と、小さいながら美しい社殿を持った神域がありました。
正午前後、日光上鉢石宿に着いた芭蕉と曽良は午後から日光山に向かいます。
