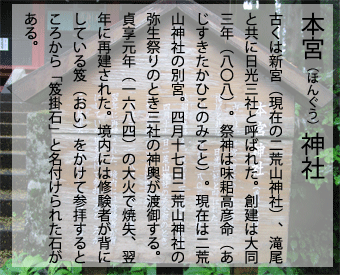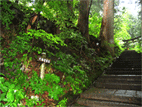この日、今年何度目かの日光は雨、それでも外国からの観光客を含めて日光山内は混雑しています。大横町の駐車場に車を止めて、大谷川に掛る日光橋を信号で渡ると正面に人影のない坂道が右へと上がって行きます。ふと引き込まれてしまいました。今まで一度も訪れた事のない本宮(ほんぐう)神社です。辺りの喧騒から離れて社殿で手を合わせます。人ごみの東照宮は外から眺めただけで二荒山神社へと向かいました。二荒山神社の山門から神社を望みます。
2010,06.14
日光の芭蕉・元禄二年(1689年) |
||
旧暦 |
新暦 |
場所 |
| 4月1日 | 5月19日 | 鹿沼を出て日光上鉢石宿の五左衛門方に滞在する。日光山参拝。本文中は30日と書かれています。 |
| 5月20日 | 裏見の滝から憾満ケ淵を散策。一旦宿に戻り、瀬尾・川室を経て、大渡りで鬼怒川を渡る。日光北街道を進み玉入で泊る。 | |
| 4月3日 | 5月21日 | 玉入より坂道を登り下りして山を越える。矢板に出て沢集落の辺りで那珂川の支流・箒川を越えて黒羽に向かう。 |
卯月朔日(四月一日)、御山(日光山)に詣拝す。往昔、此御山を「二荒山」と書しを、空海大師開基の時(弘法大師空海の伝承もあるが勝道・しょうどう・上人の開基)、「日光」と改給ふ。千歳未来をさとり給ふにや、今此御光一天にかゝやきて、恩沢八荒(おんだたくはっこう・恵みが国中に)にあふれ、四民安堵の栖(すみか)穏なり。猶、憚多くて筆をさし置ぬ。
あらたうと青葉若葉の日の光
黒髪山(二荒山神社奥の院の男体山)は霞かゝりて、雪いまだ白し。
剃捨て黒髪山に衣更 曽良
曽良は河合氏にして惣五郎と云へり。芭蕉の下葉に軒をならべて、予が薪水(台所仕事)の労をたすく。このたび松しま・象潟の眺共にせん事を悦び、且は羈旅(きりょ・旅の意)の難をいたわらんと、旅立暁(たびたつあかつき)髪を剃て墨染にさまをかえ、惣五を改て宗悟とす。仍(よっ)て黒髪山の句有。「衣更」の二字、力ありてきこゆ。
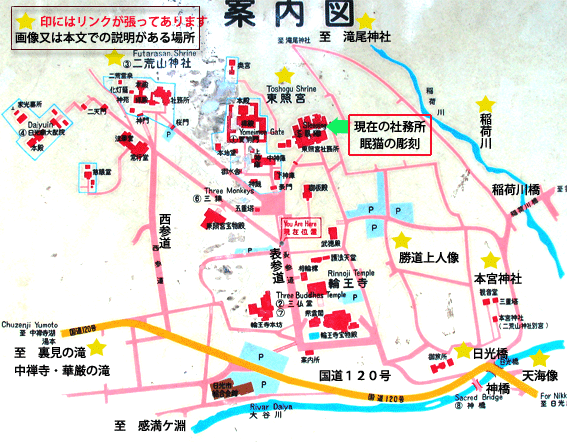
|
||||
 |
 |
|||
| 天海大僧正の像・現代の作です。家康の神号を「東照大権現」とし遺体を久能山から日光山に改葬・幕府の威信高揚に尽くす。 | ||||
 |
 |
|||
| 国道120号に掛る日光橋から大谷川。この橋のすぐ上流には真っ赤な「神橋」が掛っています。翌4月2日、ここから約2キロ強下流で芭蕉と曽良はこの川を左岸へと渡り瀬尾を経て鬼怒川の大渡りへと向かうのです。 | ||||
|
||||
 |
 |
|||
|
日光開山の勝道(しょうどう)上人が蓑を掛けたと云う伝承のある岩。恐れ多い事ですが休息の為に腰を掛けた方が具合の良いような岩でした。 |
|||
曽良旅日記:日光山参拝
一 四月朔日 前夜ヨリ小雨降。辰上刻、宿ヲ出。止テハ折々小雨ス。終日雲、日光ヘ着。雨止。清水寺(江戸のせいすいじ)ノ書、養源院(大楽院の付属寺院)ヘ届。大楽院(東照宮御別所・社務所・地図参照)ヘ使僧ヲ被添。折節大楽院客有之、未ノ下剋迄待テ御宮拝見。終テ其夜日光鉢石町五左衛門ト云者ノ方ニ宿。壱五弐四。
| 緩やかな坂を左に三仏堂を登ります。駐車場の入口に日光山を開いた勝道(しょうどう)上人の像が建っています。あまり関心を持つ人も少ないのか横には世界遺産の看板が建っています。 |
|
 |
①参考書:新潮社・奥の細道を歩く・井本農一著
 いくつかの類書の中から新潮社・奥の細道を歩く・井本農一、村松友次・土田ヒロミ著を選びました。私を引き付けた最大の点は、芭蕉はどのように感動し、著者はどう感じたかが透けて見えるからです。故事来歴をただ書き連ねている教科書的な類書に見られない面白さです。原文を読む事に工夫を凝らしてくれているので芭蕉の生の感動が伝わってくるのです。新潮社・奥の細道を歩く・井本農一、村松友次・土田ヒロミ著。 いくつかの類書の中から新潮社・奥の細道を歩く・井本農一、村松友次・土田ヒロミ著を選びました。私を引き付けた最大の点は、芭蕉はどのように感動し、著者はどう感じたかが透けて見えるからです。故事来歴をただ書き連ねている教科書的な類書に見られない面白さです。原文を読む事に工夫を凝らしてくれているので芭蕉の生の感動が伝わってくるのです。新潮社・奥の細道を歩く・井本農一、村松友次・土田ヒロミ著。②芭蕉日光山訪問の様子:上記参考書によるクリック
曽良の旅日記によると,江戸・清水(せんすい)寺から紹介された水戸家由来の小寺院・養源院が東照宮拝観の手助けをしてくれた。当時、東照宮では大修理が行われており、当日も午前中から作業の為幕府御用絵師・狩野探信が門人一同と訪れていた。そのため芭蕉と曽良は午後2時頃まで待たされたらしい。 |
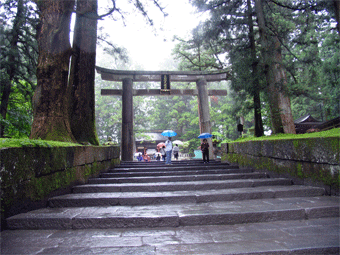 東照大権現の扁額の掛る大きな鳥居。混雑する陽明門の辺りよりこの鳥居の辺りの静寂を好みます。辺りには杉の巨木が散見されます。
東照大権現の扁額の掛る大きな鳥居。混雑する陽明門の辺りよりこの鳥居の辺りの静寂を好みます。辺りには杉の巨木が散見されます。
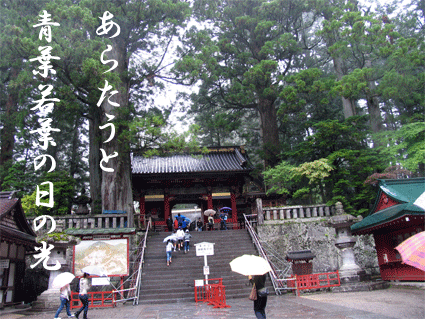 雨の中ですが陽明門への階段からは人の列が見えます。東照宮は階段の下から手を合わせてすぐに二荒山神社に向かいます。広い砂利道の両側は大きな杉並木。
雨の中ですが陽明門への階段からは人の列が見えます。東照宮は階段の下から手を合わせてすぐに二荒山神社に向かいます。広い砂利道の両側は大きな杉並木。
奥の細道で「黒髪山(二荒山神社奥の院の男体山)は霞かゝりて、雪いまだ白し」と述べた黒髪山(男体山)を御神体として祀る二荒山神社です。日光山内でも東照宮に比べると幾分静寂が保たれた空間が広がります。今日は雨空、空に何も見る事はできません。男体山は日光市内からはかなり広い地域で見られるのですが果してこの森の中から見えるのでしょうか。2010,06.14
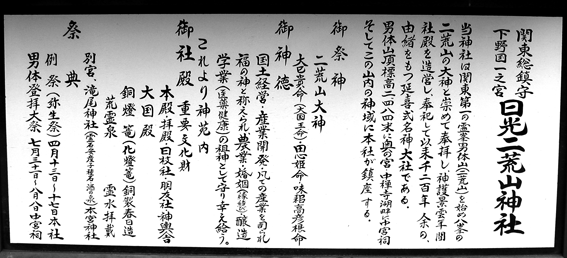
 桜門を通って二荒山神社境内へと入ります。奥に拝殿の大きな屋根が見えます。お祓いを受けるのか車が境内まで入ってきていました。
桜門を通って二荒山神社境内へと入ります。奥に拝殿の大きな屋根が見えます。お祓いを受けるのか車が境内まで入ってきていました。 |
 |

|
東照宮から赤い看板の角を左に折れて、大きな杉木立の道を二荒山神社に向かいます。東照宮の喧騒が嘘のように静かな砂利道です。桜門をくぐると二荒山神社の境内、雨に煙っています。 |
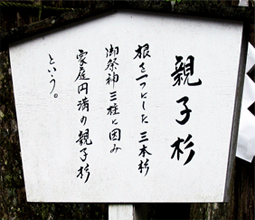 |
 |
|
|
 神門から西参道を下り表参道へと出ました。二荒山神社で芭蕉の影を思い出して静まった心持を出来る限り壊さないように、喧騒を避けながら鉢石宿へと下りました。雨は降り止む事がありません。村を出る時長靴まで用意してきたと云うのに車に忘れてきてしまいました。お陰で靴下までびっしょり、いつもながらずぼらな我が身を呪ったのです。
神門から西参道を下り表参道へと出ました。二荒山神社で芭蕉の影を思い出して静まった心持を出来る限り壊さないように、喧騒を避けながら鉢石宿へと下りました。雨は降り止む事がありません。村を出る時長靴まで用意してきたと云うのに車に忘れてきてしまいました。お陰で靴下までびっしょり、いつもながらずぼらな我が身を呪ったのです。