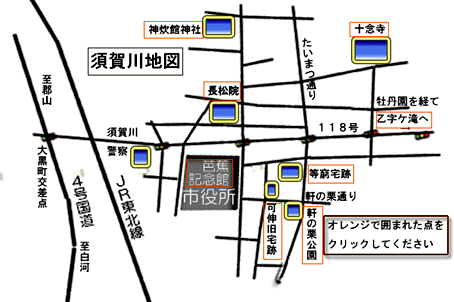 |
ژs“à‚ة“ü‚é‚ئ‰E‚ةگ{‰êگىŒxژ@ ‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·پAژں‚ھژs–ًڈٹ‚إ‚·پBژs–ًڈٹ‚ج’“ژشڈê‚ةژش‚ً“ü‚ê‚ؤپAˆêٹp‚ة‚ ‚é”mڈش‹L”Oٹظ‚ً–K‚ث‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚ح‹L”Oٹظ‚جژüˆح‚ة‚ ‚é‘ٹ—ا“™‹‡—R—ˆ‚جڈêڈٹ‚ً–K‚ث‚ؤ‚ف‚ـ‚·پBژs–ًڈٹ‚ـ‚إ‚حپA‚i‚q“Œ–kگüگ{‰êگى‰w‚©‚ç‚ح‚PپD‚TƒLƒچ‚ظ‚ا—£‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إ•à‚‚ة‚ح‚©‚ب‚艓‚¢‹——£‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·پAژں‚ھژs–ًڈٹ‚إ‚·پBژs–ًڈٹ‚ج’“ژشڈê‚ةژش‚ً“ü‚ê‚ؤپAˆêٹp‚ة‚ ‚é”mڈش‹L”Oٹظ‚ً–K‚ث‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚ح‹L”Oٹظ‚جژüˆح‚ة‚ ‚é‘ٹ—ا“™‹‡—R—ˆ‚جڈêڈٹ‚ً–K‚ث‚ؤ‚ف‚ـ‚·پBژs–ًڈٹ‚ـ‚إ‚حپA‚i‚q“Œ–kگüگ{‰êگى‰w‚©‚ç‚ح‚PپD‚TƒLƒچ‚ظ‚ا—£‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إ•à‚‚ة‚ح‚©‚ب‚艓‚¢‹——£‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚©‚°ڈہ‚©‚ç”mڈش‚ئ‘]—ا‚حگ{‰êگى‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚·پBگ{‰êگى‚إ‚ح”oگl‚إ‚ ‚é—FپA‘ٹ—ا“™‹‡‚ً–K‚ث‚ؤ‚V”‘‚ج’·‚«‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤ‘طچف‚µ‚ـ‚·پi‚±‚±‚ة‚à‰œ‚جچד¹‚ج‚SپA‚T“ْ‚ئژ–ژہ‚ئ‚حˆظ‚ب‚é‹Lڈq‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پjپB‚©‚°ڈہ‚©‚ç‚Sچ†گü‚ة–ك‚è‚ـ‚·پBچ‘“¹‚Sچ†گü‚ًگ{‰êگى‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ–kڈمپA‘هچ•’¬‚جŒًچ·“_‚ةژs–ًڈٹ‚ج“¹کH•Wژ¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚±‚ھ‚P‚P‚Wچ†گü‚ئ‚جŒًچ·“_پA‚»‚±‚ً‰Eگـ‚µ‚ؤژs–ًڈٹ‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚·پB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
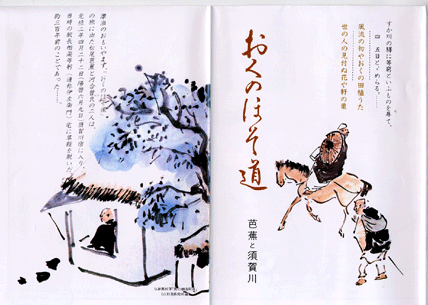 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘ٹٹy“™‹‡‚جŒؤڈج‚ة‚آ‚¢‚ؤپF‘ٹٹy“™çZ‚حگ{‰êگى‰w’·‚ب‚ا‚à‹خ‚كپAژsˆن‚جگ¶ٹˆ‚إ‚ح’تڈجپE‘ٹٹyˆةچ¶‰q–ه‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB”oگl‚ئ‚µ‚ؤ‚ج“™çZ‚ح”oچ†پE“™çZپi‹‡پjپA“ل’PچضپA“،çZ‚ئ‚àڈج‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰œ‚جچד¹‚ج’†‚إ”mڈش‚ح“™‹‡‚ئ‹L‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚±‚إ‚à”mڈش‚ة‚ب‚ç‚¢“™‹‡‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB2008.5.21
پ@پ@پ@•——¬‚جڈ‰‚₨‚‚ج“cگA‚¤‚½
–³‰؛‚ة‚±‚¦‚ق‚à‚³‚·‚ھ‚ة‚ئŒê‚ê‚خپAکeپA‘وژO‚ئ‚آپU‚¯‚ؤپAژOٹھ‚ئ‚ب‚µ‚تپB
چںڈh‚ج–T‚ةپA‘ه‚«‚ب‚éŒI‚ج–ط‰A‚ً‚½‚ج‚ف‚ؤپAگ¢‚ً‚¢‚ئ‚س‘m—LپB“ة‚ذ‚ë‚س‘¾ژRپi‚ئ‚؟‚ذ‚낤‚ف‚â‚ـ‚àپEگ¼چs‚ھ‰ج‚ة‰r‚ٌ‚¾گ[ژR‚à‚©‚‚â‚ئپj‚à‚©‚‚â‚ئپA‚µ‚أ‚©‚ةٹo‚ç‚ê‚ؤپA‚à‚ج‚ةڈ‘•tژکƒ‹پi‚©‚«‚آ‚¯‚ح‚ׂéپjپB‘´ژŒپi‚»‚ج‚±‚ئ‚خپjپAŒI‚ئ‚¢‚س•¶ژڑ‚حگ¼‚ج–ط‚ئڈ‘‚ؤپAگ¼•ûڈٍ“y‚ة•ض‚ ‚è‚ئپAچsٹî•ىژF‚جپAˆêگ¶پAڈٌ‚ة‚à’Œ‚ة‚àپAچں–ط‚ً—p‹‹پi‚à‚؟‚¢‚½‚ـپj‚س‚ئ‚©‚âپBپ@پ@پ@گ¢‚جگl‚جŒ©•t‚ت‰ش‚⌬‚جŒI
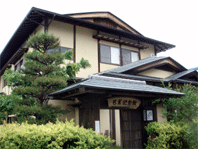 |
 |
 |
| ژs–ًڈٹ‚ج‰،‚ة”mڈش‹L”Oٹظ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBژs–ًڈٹ‚ج’“ژشڈê‚ةژش‚ًژ~‚ك‚ؤگq‚ث‚é‚ئ•¶Œ|ˆُ‚ج•û‚ھگeگط‚ة‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پBڈم‚جژتگ^‚جپh”mڈش‚ئگ{‰êگىپh‚جƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg‚ھ–ل‚¦‚ـ‚·پB | ”mڈش‹L”Oٹظ‚ج‘O‚ةŒأ‚¢‰ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB’†‚ً”`‚‚ئ‘ ‚ھٹô‚آ‚à‚ ‚é—lژq‚إ‚µ‚½پBŒم‚ë‚ةƒAƒ“ƒeƒi‚ھŒ©‚¦‚é•س‚è‚ھ”mڈش‚ھ‘طچف‚µ‚½‘ٹ—ا“™‹‡‘îگصپB | |
 |
 |
ژs–ًڈٹ‚ج‹ك‚‚ة‚حپi‚Tپ`‚U•ھپj‘ٹ—ا“™‹‡‚ج‹Œ‘îگص‚ئŒ¬‚جŒIپE‰آگLˆء‚جگص‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBˆؤ“à”آ‚ة‚»‚ء‚ؤ•à‚‚ئٹô‚آ‚©‚جŒأ‚¢‰ئ‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پBƒKƒ‰ƒ“ƒhƒE‚جٹدŒُ—p‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB”mڈش‚ًŒ}‚¦‚½گlپX‚جژq‘·‚ھژç‚ء‚ؤ‚«‚½گ¶‚«‚½’¬•ہ‚إ‚·پB”mڈش‚ھ•à‚¢‚½‚إ‚ ‚낤’ت‚è‚ة—§‚آ‚ئ”mڈش‚ج‘§گپ‚ًٹ´‚¶‚ـ‚·پBکH’n‚ھ‚ ‚èŒأ‚¢‰ئ•ہ‚ف‚ئگV‚µ‚¢‰ئ‚ھچ¬چف‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ꂱ‚»‚ھٹˆ‚«‚½’¬‚إ‚·پB |

ٹ´‚¶‚ج—ا‚¢کH’n‚ًگi‚ٌ‚إ‚¢‚‚ئŒI‚ج–ط‚ھ—§‚آˆêٹp‚ةڈo‚ـ‚·پB‘m‚ھ‰B“ظ‚·‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚àگڈ•ھ‚ئ‹·‚¢ڈêڈٹ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚½پB |
 پ@پ@ پ@پ@
‘ٹ—ا“™‹‡‘î‚ج‰،‚ةپi‘½•ھپAچL‚¢“™‹‡‘î‚ج•~’n“à‚جˆêٹp‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پjŒI‚ج–ط‚ج‰؛‚جˆء‚ة‰Bگ±‚·‚é‘mپE‰آگL‚ھ‹ڈ‚½‚±‚ئ‚ًڈ‘‚«ژc‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚±‚حŒ¬‚جŒI‚ئ‚àڈج‚³‚ê‚é‚»‚جˆء‚جگص‚إ‚·پB‘ٹ—ا‰ئٹٌ‘،‚ج‚S‘م–ع‚جŒI‚ج–ط‚ھگA‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
||||||||||||
|
|||||||||||||
 گ¢‚جگl‚جŒ©•t‚ت‰ش‚â گ¢‚جگl‚جŒ©•t‚ت‰ش‚â
Œ¬‚جŒI •¶گ”ھ”Nپi‚P‚W‚Q‚Tپj‚ة—§‚ؤ‚ç‚ꂽ‰ج”è‚إ‚·پBŒ¬‚جŒI‚ج•~’n“à‚جچ¶‘¤‚ة—§‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“–ژ‚ج’n•û‚ةڈZ‚ـ‚¤گlپX‚جˆê•”‚ةپAچ‚‚¢•¶‰»“I‘f—{‚ھچف‚ء‚½ژ–‚ة‰œ‚جچד¹‚جگص‚ً’H‚é‚ئ•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB“–ژ‚ج•¶‰»“I‹³—{‚ً“ْڈي“I‚ة‚½‚µ‚ب‚ٌ‚إ‚¢‚½•گژmٹK‹‰ˆبٹO‚ة‚àچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپA’¬گl‚ج—ح‚جچ‚‚ـ‚è‚جŒ»‚ê‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB”mڈش‚ج‚¨‚ئ‚أ‚ê‚é’n‚إ‚حپA”o‹ه‚ً’ت‚µ‚ؤگg•ھ‚ً‰z‚¦‚½‚آ |
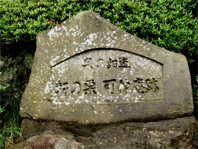 ”mڈش‚ح‚UŒژ‚P‚O“ْ‚ة‰آگL‚ً–K‚ث‚½Œم‚àپAگ{‰êگى‘طچف’†‚à‰½“x‚©–K‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰آگL‚ح”oگl‚إچ†‚ًŒIچض‚ئڈج‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘mŒ`‚جژز‚إ‚ح‚ ‚ء‚½‚ھپA–{—ˆ‚جˆس–،‚ج‘m‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ”mڈش‚ح‚UŒژ‚P‚O“ْ‚ة‰آگL‚ً–K‚ث‚½Œم‚àپAگ{‰êگى‘طچف’†‚à‰½“x‚©–K‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰آگL‚ح”oگl‚إچ†‚ًŒIچض‚ئڈج‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘mŒ`‚جژز‚إ‚ح‚ ‚ء‚½‚ھپA–{—ˆ‚جˆس–،‚ج‘m‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
—‚‚P‚P“ْپA“™‹‡‘î‚ح“cگA‚¦‚إ‘½–Z‚ً‹ة‚ك‚éپB”mڈش‚ئ‘]—ا‚حŒكŒم‚©‚ç‰آگL‚جˆء‚ً–K‚ثپAگ{‰êگىچف‚ج”oگl‚½‚؟‚ئ‰جگه‚ًٹھ‚¢‚½پiٹب—ھ‚ةŒ¾‚¦‚خکA‹ه‚ج‹ه‰ïپjپBپw‰B‰ئ‚₽‚¾‚ت‰ش‚ًŒ¬‚جŒIپx‚ئ“ا‚قپB‰آگL‚ج‰ئ‚إ‚حژ₵‚°‚بŒI‚ج‰ش‚ھ–[‚ة‚ب‚ء‚ؤچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |
||||||||||||
|
|||||||||||||
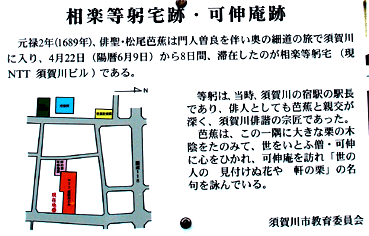 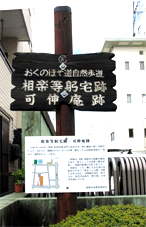 Œ¬‚جŒI’뉀‚ًچ¶‚ة‹ب‚ھ‚é‚ئ‚m‚s‚s‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚±‚ة‘ٹ—ا“™‹‡‘îگص‚ج•Wژ¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB”ٌڈي‚ةچL‘ه‚ب–تگد‚إ‚·پB Œ¬‚جŒI’뉀‚ًچ¶‚ة‹ب‚ھ‚é‚ئ‚m‚s‚s‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚±‚ة‘ٹ—ا“™‹‡‘îگص‚ج•Wژ¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB”ٌڈي‚ةچL‘ه‚ب–تگد‚إ‚·پB
ٹe’n‚ةڈZ‚قژ‘ژY‰ئ‚â’n•û‚ج•گ‰ئ‚ھچ‚‚¢‹³—{‚ًژ‚؟پAچ]Œث‚ج•¶‰»‚ة‹‚¢“²‚ê‚ً‚¢‚¾‚¢‚ؤ‚¢‚½ژ–‚ةژv‚¢‚ھ‚¢‚«‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA‘ٹ—ا“™‹‡‚ھ‘§‚أ‚‚±‚ج’n‚ة—§‚آ‚ئپA“كگ{‚ج“ٌڈh‚جڈh‚جچ‚‹vٹoچ¶‰q–ه‚ًژv‚¢ڈo‚³‚¸‚ة‚ح‚¢‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚ظ‚عپA“¯‚¶–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB”mڈش‚ج—·‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚بژ‘ژY‰ئٹK‹‰‚جگlپX‚ج‘¶چف‚ھ‚ ‚ء‚ؤڈ‰‚ك‚ؤژہ‚è‚ ‚é‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB |
|||||||||||||
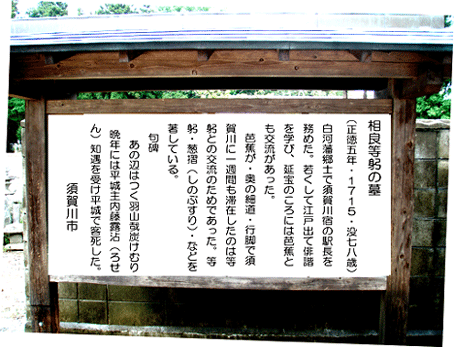 “™‹‡‹Œ‘îگص‚©‚çپA‹ك‚‚ج’·ڈ¼‰@‚ً–K‚ث‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB‚±‚±‚ة‚ح‘ٹ—ا“™‹‡‚ج‚¨•و‚ئ‹ه”è‚ھ‚ ‚é‚ئ‚جژ–‚إ‚·پB‚½‚¾پAژ„‚ج–K‚ث‚½“ْ‚ح‘ه‚«‚ب‘’‹V‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپAŒ©ٹw‚ًçSçO‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB “™‹‡‹Œ‘îگص‚©‚çپA‹ك‚‚ج’·ڈ¼‰@‚ً–K‚ث‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB‚±‚±‚ة‚ح‘ٹ—ا“™‹‡‚ج‚¨•و‚ئ‹ه”è‚ھ‚ ‚é‚ئ‚جژ–‚إ‚·پB‚½‚¾پAژ„‚ج–K‚ث‚½“ْ‚ح‘ه‚«‚ب‘’‹V‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپAŒ©ٹw‚ًçSçO‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
‹·‚¢‹«“à‚ج“ü‚èŒû‚©‚ç’†‚ً‚¤‚©‚ھ‚ء‚ؤ‚©‚çپAژَ•t‚ة‹ڈ‚éگl‚ة‚¨‚¸‚¨‚¸‚ئپA‘ٹ—ا“™‹‡‚ج‚¨•و‚ًŒ©‚ةچs‚ء‚ؤ‚à—ا‚¢‚©‚ئ•·‚¢‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB—¹‰ً‚ً“¾‚ؤ‚©‚ç‹}‚¢‚إ‘’‹V‚ج—ٌ‚ً‰I‰ٌ‚µ‚ؤ–{“°‚ج— ژè‚ة‰ٌ‚è‚ـ‚µ‚½پB — ژè‚ة‰ٌ‚ء‚½‚ç‚ ‚؟‚炱‚؟‚ç‚ة“ü‚èŒû‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚©‚ب‚è‘ه‚«‚ب‚¨ژ›‚إ‚µ‚½پB “™‹‡‚جگà–¾”آ‚ة‚V‚WچثپA‚P‚V‚P‚T”N‚ة•½‚إ‹qژ€‚ئ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB“™‹‡‚ج‹ه”è‚ھ‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·‚ھ‚ب‚ة‚©‘’‹V‚جژ×–‚‚ً‚µ‚ؤ‚ح‚ئ’T‚·‚±‚ئ‚ً‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 ڈàکO‚ج•س‚è‚ھ’·ڈ¼‰@پA‚±‚ج‚و‚¤‚ب‰ش—ض‚ھˆح‚ق‚و‚¤‚ةڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¨ژ›‚إ‚ح‘ه‚«‚ب‘’‹V‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA‘ٍژR‚جگlپX‚ھڈo“ü‚è‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB–ه‘O‚ًچs‚«‚آ–ك‚è‚آ‚µ‚ـ‚µ‚½پB ڈàکO‚ج•س‚è‚ھ’·ڈ¼‰@پA‚±‚ج‚و‚¤‚ب‰ش—ض‚ھˆح‚ق‚و‚¤‚ةڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¨ژ›‚إ‚ح‘ه‚«‚ب‘’‹V‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA‘ٍژR‚جگlپX‚ھڈo“ü‚è‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB–ه‘O‚ًچs‚«‚آ–ك‚è‚آ‚µ‚ـ‚µ‚½پB |
 ’·ڈ¼‰@–{“°‚ج— ‚ة“™‹‡‚ج•و’n‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج“r’†پAٹ™‘qژ‘م“ٌٹK“°ژپ‚ة‚و‚ء‚ؤ’z‚©‚ꂽگ{‰êگىڈé‚جˆâچ\‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚P‚S‚S‚W”N“ٌٹK“°ˆ×ژپ‚ة‚و‚ء‚ؤگ®”ُ‚³‚êپA‚P‚T‚W‚X”Nˆة’Bگڈ@‚ةچUŒ‚‚³‚ê—ژڈé‚·‚é‚ـ‚إگ{‰êگى‚ج‹ŒژsٹX’nˆê‘ر‚ة‘¶چف‚µ‚½‚ئ‚جگà–¾”آ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ح“y—غ‚ئ‹َ–x‚جˆâچ\‚إ‚·پB ’·ڈ¼‰@–{“°‚ج— ‚ة“™‹‡‚ج•و’n‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج“r’†پAٹ™‘qژ‘م“ٌٹK“°ژپ‚ة‚و‚ء‚ؤ’z‚©‚ꂽگ{‰êگىڈé‚جˆâچ\‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚P‚S‚S‚W”N“ٌٹK“°ˆ×ژپ‚ة‚و‚ء‚ؤگ®”ُ‚³‚êپA‚P‚T‚W‚X”Nˆة’Bگڈ@‚ةچUŒ‚‚³‚ê—ژڈé‚·‚é‚ـ‚إگ{‰êگى‚ج‹ŒژsٹX’nˆê‘ر‚ة‘¶چف‚µ‚½‚ئ‚جگà–¾”آ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ح“y—غ‚ئ‹َ–x‚جˆâچ\‚إ‚·پB |
|||||||||||||
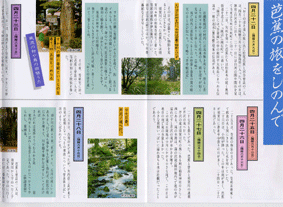 |
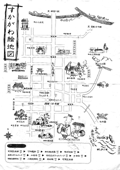 ژs–ًڈٹ‚ج‰،‚ة‚ ‚é–³—؟‚جژ‘—؟ٹظ‚إ‚·پBژ„‚à‰½‹C‚ب‚–K‚ê‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½‚ھپAٹwŒ|ˆُ‚ج•û‚ھڈ‡کH‚ًگeگط‚ة‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½پBƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg—ق‚ج“à—e‚àڈ[ژہ‚µ‚ؤ‚¨‚è‘ه•د—Lˆس‹`‚ب–K–â‚إ‚µ‚½پB‚¦‚ؤ‚µ‚ؤ‚±‚ج‚و‚¤‚بڈêچ‡پA•¨ژY”ج”„‚â”mڈش‚ًژg‚ء‚ؤ‚ج’¬‹»‚µ‚جچ°’_‚ھ“§‚¯‚ؤŒ©‚¦‚éڈêچ‡‚ھڈ‚ب‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚حژd•û‚ج‚ب‚¢–ت‚à‚ ‚邱‚ئ‚ًڈdپXڈ³’m‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAچT‚¦‚ك‚إ‚ ‚é‚ب‚ç‚خ—·‚جٹy‚µ‚³‚ً‘¹‚ب‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·پBگ{‰êگى‚ح‰ں‚µ•t‚¯‚ھ‚ـ‚µ‚³‚ھ‚ب‚پA”mڈش‚جژp‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂ邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚½‘ه•دˆس‹`گ[‚¢‰œ‚جچד¹‚ً‚½‚ا‚é—·‚ًٹy‚µ‚ك‚ـ‚µ‚½پBگ{‰êگى‚ة”mڈش‚جگص‚ً’H‚é‚ئ‚«‚ة‚ح‚±‚ج‹L”Oٹظ‚ًچإڈ‰‚ج–K–â’n‚ة‘I‚ش‚±‚ئ‚ً‚¨ٹ©‚ك‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB ژs–ًڈٹ‚ج‰،‚ة‚ ‚é–³—؟‚جژ‘—؟ٹظ‚إ‚·پBژ„‚à‰½‹C‚ب‚–K‚ê‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½‚ھپAٹwŒ|ˆُ‚ج•û‚ھڈ‡کH‚ًگeگط‚ة‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½پBƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg—ق‚ج“à—e‚àڈ[ژہ‚µ‚ؤ‚¨‚è‘ه•د—Lˆس‹`‚ب–K–â‚إ‚µ‚½پB‚¦‚ؤ‚µ‚ؤ‚±‚ج‚و‚¤‚بڈêچ‡پA•¨ژY”ج”„‚â”mڈش‚ًژg‚ء‚ؤ‚ج’¬‹»‚µ‚جچ°’_‚ھ“§‚¯‚ؤŒ©‚¦‚éڈêچ‡‚ھڈ‚ب‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚حژd•û‚ج‚ب‚¢–ت‚à‚ ‚邱‚ئ‚ًڈdپXڈ³’m‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAچT‚¦‚ك‚إ‚ ‚é‚ب‚ç‚خ—·‚جٹy‚µ‚³‚ً‘¹‚ب‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·پBگ{‰êگى‚ح‰ں‚µ•t‚¯‚ھ‚ـ‚µ‚³‚ھ‚ب‚پA”mڈش‚جژp‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂ邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚½‘ه•دˆس‹`گ[‚¢‰œ‚جچד¹‚ً‚½‚ا‚é—·‚ًٹy‚µ‚ك‚ـ‚µ‚½پBگ{‰êگى‚ة”mڈش‚جگص‚ً’H‚é‚ئ‚«‚ة‚ح‚±‚ج‹L”Oٹظ‚ًچإڈ‰‚ج–K–â’n‚ة‘I‚ش‚±‚ئ‚ً‚¨ٹ©‚ك‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB |
||
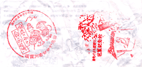 ‹L”Oٹظ‚إ‚حڈم‚جژتگ^‚جƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg‚ھ–ل‚¦‚ـ‚·پBگ{‰êگى‚ج‚إ‚ج”mڈش‚ج‘«گص‚ھڈعچׂة‹L‚³‚ꂽٹy‚µ‚¢’nگ}•t‚«ژ‘—؟‚إ‚·پBپ–ژ„‚àژQچlژ‘—؟‚ئ‚µ‚ؤژg—p‚³‚¹‚ؤ–ل‚ء‚½ژ–‚ً‹L‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB’¬•à‚«‚ة‚ح‰Eڈم‚ج’nگ}‚ً–ل‚¤‚ئ‘ه•د•ض—ک‚إ‚·پB ‹L”Oٹظ‚إ‚حڈم‚جژتگ^‚جƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg‚ھ–ل‚¦‚ـ‚·پBگ{‰êگى‚ج‚إ‚ج”mڈش‚ج‘«گص‚ھڈعچׂة‹L‚³‚ꂽٹy‚µ‚¢’nگ}•t‚«ژ‘—؟‚إ‚·پBپ–ژ„‚àژQچlژ‘—؟‚ئ‚µ‚ؤژg—p‚³‚¹‚ؤ–ل‚ء‚½ژ–‚ً‹L‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB’¬•à‚«‚ة‚ح‰Eڈم‚ج’nگ}‚ً–ل‚¤‚ئ‘ه•د•ض—ک‚إ‚·پB |
ڈ‡کHپFگ{‰êگىژs‡@‚i‚q“Œ–kگüگ{‰êگى‰w‚©‚çƒoƒX‚إ–ٌ‚P‚O•ھپB’†’¬”ھ”¦’¬‰؛ژش‡A“Œ–k“¹گ{‰êگىƒCƒ“ƒ^پ[‚©‚ç–ٌ‚P‚O•ھپiژs–ًڈٹ’“ژشڈê‚ةژ~‚ك‚ç‚ê‚ـ‚·پj ڈZڈٹپFگ{‰êگىژs”ھ”¦’¬‚P‚R‚UپE‚O‚Q‚S‚Wپ|‚V‚Qپ|‚P‚Q‚P‚Qپ@ ‚»‚ج‘¼پFŒژ—j‹xٹظپEŒك‘O‚P‚Oپ`ŒكŒم‚TژپE“üڈê–³—؟ | ||

ژè‘إ‚؟‹¼”پu‚©‚ا‚âپv0248-72-1584 |
 ژs–ًڈٹ‚ج‚ ‚½‚è‚إ’‹گH‚ً‚ئ‚낤‚ئ’ت‚è‚ھ‚©‚è‚جگl‚ةگq‚ث‚é‚ئپu‚©‚ا‚âپv‚ئŒ¾‚¤‹¼”‰®‚³‚ٌ‚ً‹³‚¦‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB’nŒ³‚إ•]”»‚ج“X‚ً–K‚ê‚邱‚ئ‚حپA‚»‚ج“y’n‚جگl‚جگH‚ו¨‚ج–،•t‚¯‚âچD‚ف‚ھ•ھ‚©‚è‘ه•د‹»–،گ[‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB“Vگ·‚苼”پiپڈ‚W‚T‚O’ِ‚إ‚µ‚½پj‚ًگH‚ׂؤŒ©‚ـ‚µ‚½پBگ·‚è•t‚¯‚ھپu‚ض‚¬‹¼”پv•—‚إ‚µ‚½پBژ„‚ة‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ‹¼”‚ھچd‚ك‚ئٹ´‚¶‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚خژ©‘ج‚ة‚àڈ¬ژM‚ة‚à‚»‚ê‚ب‚è‚جچH•v‚ھٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·پBڈ‚µچd‚ك‚ھ‚±‚ج’n‚جچD‚ف‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBƒtƒ@ƒ~ƒٹپ[ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚ج‰وˆê“I‚ب–،‚حگH—ئپAچH•v‚جŒ©‚ç‚ê‚é–،‚ھ—؟—پi–،‚ھچ‡‚¤چ‡‚ي‚ب‚¢‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپj‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پA—·‚إ‚ح‚»‚ج’n‚ج–،‚ًٹy‚µ‚ف‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB”mڈش‹L”Oٹظ‚ج‚·‚®‹ك‚پA118چ†گüپEگ{‰êگىŒxژ@‚ج‰،‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پBپu‚©‚ا‚âپv‚جچ€‚ج‚ف ژs–ًڈٹ‚ج‚ ‚½‚è‚إ’‹گH‚ً‚ئ‚낤‚ئ’ت‚è‚ھ‚©‚è‚جگl‚ةگq‚ث‚é‚ئپu‚©‚ا‚âپv‚ئŒ¾‚¤‹¼”‰®‚³‚ٌ‚ً‹³‚¦‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB’nŒ³‚إ•]”»‚ج“X‚ً–K‚ê‚邱‚ئ‚حپA‚»‚ج“y’n‚جگl‚جگH‚ו¨‚ج–،•t‚¯‚âچD‚ف‚ھ•ھ‚©‚è‘ه•د‹»–،گ[‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB“Vگ·‚苼”پiپڈ‚W‚T‚O’ِ‚إ‚µ‚½پj‚ًگH‚ׂؤŒ©‚ـ‚µ‚½پBگ·‚è•t‚¯‚ھپu‚ض‚¬‹¼”پv•—‚إ‚µ‚½پBژ„‚ة‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ‹¼”‚ھچd‚ك‚ئٹ´‚¶‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚خژ©‘ج‚ة‚àڈ¬ژM‚ة‚à‚»‚ê‚ب‚è‚جچH•v‚ھٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·پBڈ‚µچd‚ك‚ھ‚±‚ج’n‚جچD‚ف‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپBƒtƒ@ƒ~ƒٹپ[ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚ج‰وˆê“I‚ب–،‚حگH—ئپAچH•v‚جŒ©‚ç‚ê‚é–،‚ھ—؟—پi–،‚ھچ‡‚¤چ‡‚ي‚ب‚¢‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپj‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پA—·‚إ‚ح‚»‚ج’n‚ج–،‚ًٹy‚µ‚ف‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB”mڈش‹L”Oٹظ‚ج‚·‚®‹ك‚پA118چ†گüپEگ{‰êگىŒxژ@‚ج‰،‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پBپu‚©‚ا‚âپv‚جچ€‚ج‚ف |
|
||||||||
|
Copyright (C) Oozora.All Right Reserved.
|
||||||||

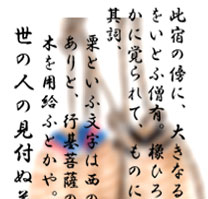
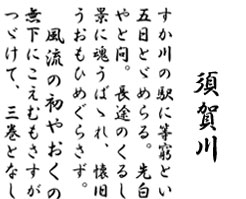
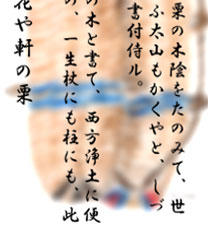
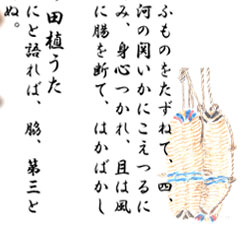
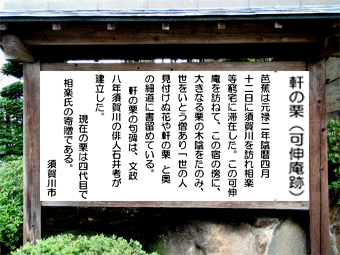
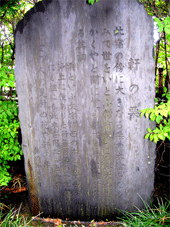
 ‚ب‚ھ‚è‚ھ‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پBژ‚ئ‚µ‚ؤڈ—گ«‚à‹ڈ‚邱‚ئ‚حژ„‚ة‚ح‹ء‚«‚إ‚·پB••Œڑژ‘م‚جگg•ھژذ‰ï‚ھپA—Z’ت–³ٹV‚إٹة‚â‚©‚ب–ت‚ًٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚½ژ–‚ھ—‰ًڈo—ˆ‚ـ‚·پB
‚ب‚ھ‚è‚ھ‚ھŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پBژ‚ئ‚µ‚ؤڈ—گ«‚à‹ڈ‚邱‚ئ‚حژ„‚ة‚ح‹ء‚«‚إ‚·پB••Œڑژ‘م‚جگg•ھژذ‰ï‚ھپA—Z’ت–³ٹV‚إٹة‚â‚©‚ب–ت‚ًٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚½ژ–‚ھ—‰ًڈo—ˆ‚ـ‚·پB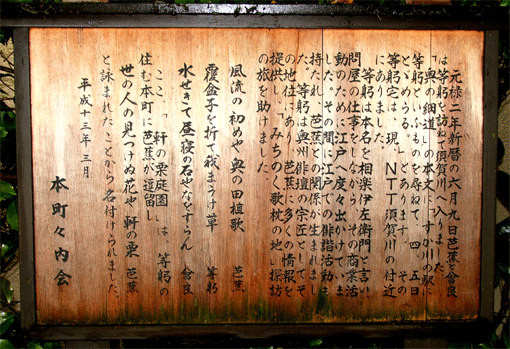 ‰آگLˆءگص‚جکH’n‚ًگi‚ق‚ئ‰½‚ئ‚àژï‚«‚ج‚ ‚éپhŒ¬‚جŒI’ت‚èپh‚ةڈo‚ـ‚·پB‚»‚±‚ًچ¶گـ‚µ‚ؤ‚½‚¢‚ـ‚آ’ت‚è‚ةŒü‚©‚¤‚ئپA‰Eٹp‚ة’¬“à‰ïٹا—‚جپhŒ¬‚جŒI’뉀پh‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBگ{‰êگى–¼•¨‚جƒ{ƒ^ƒ“‚ج‹GگكپA’뉀‚جˆêٹp‚ًڈü‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‰آگLˆءگص‚جکH’n‚ًگi‚ق‚ئ‰½‚ئ‚àژï‚«‚ج‚ ‚éپhŒ¬‚جŒI’ت‚èپh‚ةڈo‚ـ‚·پB‚»‚±‚ًچ¶گـ‚µ‚ؤ‚½‚¢‚ـ‚آ’ت‚è‚ةŒü‚©‚¤‚ئپA‰Eٹp‚ة’¬“à‰ïٹا—‚جپhŒ¬‚جŒI’뉀پh‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBگ{‰êگى–¼•¨‚جƒ{ƒ^ƒ“‚ج‹GگكپA’뉀‚جˆêٹp‚ًڈü‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

 ”mڈش‚ئ‘]—ا‚جڈ¬‚³‚بگخ‘œژèچى‚è‚جٹ´‚¶‚ھ‚µ‚ؤ‘ه•دچD‚ـ‚µ‚¢’뉀‚إ‚·پB’N‚à‹ڈ‚ب‚¢ƒxƒ“ƒ`‚ةچہ‚ء‚ؤˆê‹x‚ف‚³‚¹‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB–³ڈ‚جگeگط‚ةگع‚·‚邱‚ئ‚ح—·‚جٹy‚µ‚ف‚ً‘‚µ‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB
”mڈش‚ئ‘]—ا‚جڈ¬‚³‚بگخ‘œژèچى‚è‚جٹ´‚¶‚ھ‚µ‚ؤ‘ه•دچD‚ـ‚µ‚¢’뉀‚إ‚·پB’N‚à‹ڈ‚ب‚¢ƒxƒ“ƒ`‚ةچہ‚ء‚ؤˆê‹x‚ف‚³‚¹‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB–³ڈ‚جگeگط‚ةگع‚·‚邱‚ئ‚ح—·‚جٹy‚µ‚ف‚ً‘‚µ‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB
 ’·ڈ¼‰@‚ج“üŒû‚ة‚ح‚±‚ج‘ٹٹy“™‹‡‚ج‹ه‚ھڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‹ه”è‚ح–{“a‚جچ¶‘¤‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
’·ڈ¼‰@‚ج“üŒû‚ة‚ح‚±‚ج‘ٹٹy“™‹‡‚ج‹ه‚ھڈü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‹ه”è‚ح–{“a‚جچ¶‘¤‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB


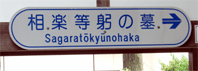

 پ@‘O‰ٌپAژ›‚إ‚ح‘’‹V‚ھژ·‚èچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‰“—¶‚µ‚½’·ڈ¼‰@‚ًچؤ“x–K‚ثپA‘ٹٹy“™‹‡‚ج‹ه”è‚ً’T‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ح–{“°‚جچ¶‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB’·ڈ¼‰@‹ه”è‚جچ€‚ج‚ف
پ@‘O‰ٌپAژ›‚إ‚ح‘’‹V‚ھژ·‚èچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‰“—¶‚µ‚½’·ڈ¼‰@‚ًچؤ“x–K‚ثپA‘ٹٹy“™‹‡‚ج‹ه”è‚ً’T‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ح–{“°‚جچ¶‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB’·ڈ¼‰@‹ه”è‚جچ€‚ج‚ف